中学生になると、友達関係の悩みが急に増えたと感じることはありませんか?
「親友と気まずくなった…」「グループに入れない気がする…」「誰にも本音が言えない…」そんな気持ちは、多くの中学生が経験しています。
このブログでは、中学生の友達関係にまつわるさまざまな悩みに寄り添い、解決のヒントをわかりやすく紹介します。
子ども自身だけでなく、保護者の方にも読んでいただきたい内容になっています。
今のつらさを少しでも軽くしたい。
そんな思いを込めて、友達との関わり方や親のサポート方法をまとめました。
仲良しのはずなのに…?友達との距離感で悩むとき
親友とちょっと気まずくなったときの対処法
中学生になると、親友との関係にちょっとしたズレやすれ違いが生まれることがあります。
いつも一緒にいたのに、最近少し距離を感じる…。
そんなときは、「自分だけがそう感じているのかな?」と不安になることもありますよね。
でも、実は相手も同じように感じているかもしれません。
まずは、落ち着いて自分の気持ちを整理しましょう。
「なんでモヤモヤしてるのかな?」と紙に書き出してみるのもおすすめです。
次に、相手に気持ちを伝えることを考えてみましょう。
「最近、ちょっと話す時間が減った気がしてさ…。
前みたいに話せたらうれしいな」など、自分の気持ちをやさしく伝えることで、誤解が解けることもあります。
また、相手が忙しかったり別のことで悩んでいる可能性もあります。
「気まずくなった=仲が悪くなった」ではないので、焦らず自然なタイミングで話しかけてみましょう。
気まずくなっても、それを乗り越えることで関係がもっと深まることもあります。
友達との関係は一生続くものではなく、変わっていくのが普通です。
でも、自分の気持ちを大切にしながら相手と向き合うことは、きっとこれからも役に立つ経験になります。
グループに入れないと感じたときはどうする?
クラスや部活などで、いつも同じメンバーで行動しているグループを見ると、自分がそこに入れない気がして不安になることがあります。
「みんな楽しそうなのに、自分だけ仲間はずれかも」と感じたことはありませんか?
でも、グループに“入らなきゃいけない”というルールはありません。
自分が無理をして合わせていると、心が疲れてしまいます。
大切なのは、「どんな人と一緒にいると自分がリラックスできるか」です。
もし今のグループに違和感を感じるなら、無理に入ろうとしなくても大丈夫。
少しずつ、自分に合った人を探していくのが自然な流れです。
趣味が似ている人や、授業中に隣の席の子とちょっと話してみるのもいいかもしれません。
また、友達の数が少ないことを気にする必要はありません。
大切なのは“数”より“質”です。
ひとりでも信頼できる友達がいれば、それで十分なんです。
人間関係は時間とともに変わります。
今はグループに入れないように感じても、半年後には自然と話せる仲になっていることもよくあります。
自分を責めず、焦らず、自然体でいることが一番大切です。
無理に話を合わせて疲れていない?
友達との会話で、話題についていけなかったり、興味がないのに笑ってしまったり…。
そんな経験はありませんか?
「みんなと仲良くしたいから」と頑張りすぎて、あとでドッと疲れてしまうこともあるでしょう。
無理に話を合わせることは、実は自分を少しずつ苦しめてしまいます。
中学生のうちは特に、「みんなと同じじゃなきゃいけない」と思いやすい時期です。
でも、みんな違っていいんです。
話が合わないなと感じたときは、無理に話に乗らず、ニコッと笑って聞いているだけでもOK。
「そうなんだ〜」と軽く受け流すスキルも大事です。
自分の好きなことや得意なことを大切にすることで、自然と気が合う友達が見つかります。
また、「合わせなきゃ」と思いすぎているときは、少し一人の時間をとって気持ちをリセットするのもおすすめです。
無理して笑うより、素の自分でいられる関係のほうがずっとラクで楽しいですよ。
友達と話すことは楽しいけれど、自分を守ることも大切です。
自分らしくいられる場所を大切にしてくださいね。
一人でいる時間も大切にしていい理由
「友達がいないと思われたくない」
「一人でいるとさみしく見えるかな?」
そんなふうに感じて、無理に誰かと一緒にいようとすることってありますよね。
でも、実は一人でいる時間もとても大切なんです。
自分の好きなことに集中したり、ゆっくり考えごとをしたり。
そういう時間があるからこそ、気持ちが落ち着いて、自分らしくいられるようになります。
一人の時間は、自分の「好き」や「得意」を見つけるチャンスです。
読書をしたり、音楽を聴いたり、イラストを描いたり。
一人でいるからこそできることって、たくさんあるんです。
また、一人でいても「寂しい」とは限りません。
「自分の時間を楽しんでる」っていう自信があれば、まわりの目も気にならなくなってきます。
一人の時間を大事にできる人は、友達との時間ももっと楽しめるようになります。
自分を大切にすることが、良い人間関係を築く第一歩なんです。
距離をとったほうがよい友達とは?
中には、「この人と一緒にいると疲れる」「いつも自分ばかり我慢している」と感じる友達もいるかもしれません。
そんなときは、その人との距離を少しとってみるのも大切な判断です。
友達だからといって、ずっと一緒にいなきゃいけないわけではありません。
相手の機嫌にふりまわされたり、自分の意見を言えなかったりする関係は、心がすり減ってしまいます。
距離をとることは、決して「裏切り」ではありません。
むしろ、自分の心を守るために必要なことなんです。
たとえば、あいさつだけはするけれど深く関わらないようにする。
話す機会を少しずつ減らしていく。
そういった「無理のない距離感」を意識することで、気持ちがラクになります。
もし誰かとの関係にモヤモヤしているなら、「この関係、本当に自分にとって大切かな?」と一度考えてみましょう。
無理に仲良くするより、自分が安心できる環境を選ぶことが、いちばん大切です。

友達ができない…そんなときどうする?
声をかけるのが怖い…最初の一歩のコツ
新しいクラスや環境では、「話しかけたいけど、なんて言えばいいかわからない」って思うことありますよね。
声をかけるのって、けっこう勇気がいります。
でも、ちょっとしたコツでその“最初の一歩”はグッとラクになります。
まずは、「あいさつ」を大切にしましょう。
「おはよう」や「おつかれさま」だけでも、相手に話しかけるチャンスになります。
毎日あいさつしているうちに、自然と会話が生まれることもあります。
次に、「共通の話題」を見つけること。
同じ授業のこと、持ち物、部活、先生の話など、話題のタネは身の回りにたくさんあります。
「そのペンかわいいね」とか、「今日の授業むずかしかったね」など、ちょっとしたひと言でいいんです。
ポイントは、完ぺきな会話じゃなくていいということ。
相手がうまく返せなかったとしても、「自分から話しかけた」ということに意味があります。
勇気を出して行動することで、少しずつ距離が縮まっていきます。
「話しかけるのが怖い」はみんなが感じることです。
だからこそ、自分のペースで、できるところから一歩ずつ進めていきましょう。
その小さな一歩が、大きなつながりにつながります。
共通点がある人を見つけるには?
友達になりやすい人って、どんな人でしょうか?
実は「共通点がある人」って、すごく仲良くなりやすいんです。
共通の趣味、好きなアニメ、部活、ゲーム、音楽…いろんなつながりがありますよね。
まずは、自分の「好きなこと」を考えてみましょう。
好きな教科、好きなキャラ、最近ハマってること。
それをちょっと周りの人に話してみると、「えっ、私もそれ好き!」と反応してくれる人がいるかもしれません。
逆に、誰かが話していることに耳をかたむけてみて、「それ私も気になってたんだ」と話しかけてみるのもアリです。
共通点は、会話のきっかけになります。
たとえば、「そのシャーペン、文房具屋さんで見たよ」とか、「昨日のテレビ見た?」なんていう話も、立派な共通点探しのスタートです。
また、委員会や部活などで同じ目標に向かっている人とは、自然に打ち解けやすくなります。
無理に仲良くしようとしなくても、共通点をきっかけに自然と距離が近くなっていきますよ。
クラス以外で友達を作る方法
クラスでなかなか友達ができないと、「自分は友達ができないタイプなんだ」と思いがちですが、実はそんなことありません。
友達はクラスだけで作るものじゃないんです。
たとえば、部活動はとても良い場所です。
同じ目標に向かって一緒に活動することで、自然と仲良くなれます。
部活の時間だけじゃなく、大会や練習で深い絆ができることも多いです。
また、習いごとや地域の活動など学校以外の場所でも、友達を作るチャンスはたくさんあります。
塾やスポーツクラブ、公民館のイベントなど、自分の「好き」を通じて知り合える人もいるんです。
他にも、オンラインの安全な場所(先生や保護者の許可がある場)で、同じ趣味をもつ仲間とつながることもできます。
「リアルじゃなくても友達になれる」という時代でもあります。
大事なのは、「ここで友達を作らなきゃ」と焦らないこと。
場所を変えることで、自分に合う友達が見つかるかもしれません。
世界は思っているより広いんです。
自分の良さに気づいてもらうには?
「どうして自分は友達ができにくいんだろう…」と悩んだとき、まず見てほしいのが自分の中の良さです。
もしかすると、あなたは気づいていないだけで、すでに周りから見て魅力的な人かもしれません。
自分の良さって、意外と自分ではわかりにくいものです。
「よく気がつくね」と言われたことがある?
「話を聞いてくれてうれしかった」と感謝されたことは?
それがあなたの“強み”なんです。
自分の良さを知るには、まず小さな自信を持つことから始めましょう。
「自分には○○ができる」「○○が好き」と言えるようになると、それが言葉や態度にも出て、相手に伝わります。
また、人の良いところに気づいて言葉にできる人は、とても魅力的です。
「その髪型いいね」「ノートきれいに書いてるね」
そんな小さなひと言が、相手との距離を縮めてくれます。
人に合わせるのではなく、自分の良さを大切に。
その自然体のあなたに惹かれる人が、きっと現れます。
友達作りで「無理しないこと」が一番大事
「友達を作らなきゃ」「仲間に入らなきゃ」
そんなふうに思いすぎて、自分を無理してしまうことがあります。
でも、一番大事なのは無理をしないことなんです。
自分を偽ってまで友達を作っても、その関係は長続きしません。
疲れてしまって、自分の心がすり減ってしまいます。
本当に仲良くなれる人とは、自然体の自分でいられるものです。
おしゃべりが得意じゃなくても、人と少し違っていても、それを受け入れてくれる友達が必ずいます。
また、「今はひとりでいる時間が多いな」と感じても、それは悪いことではありません。
それだけ、自分を見つめる時間があるということです。
焦らず、自分に合ったペースで人とつながっていくことが大切です。
無理せず、がんばりすぎず、今の自分を大切にして。
その姿が、周りにとっても魅力的に映るはずです。
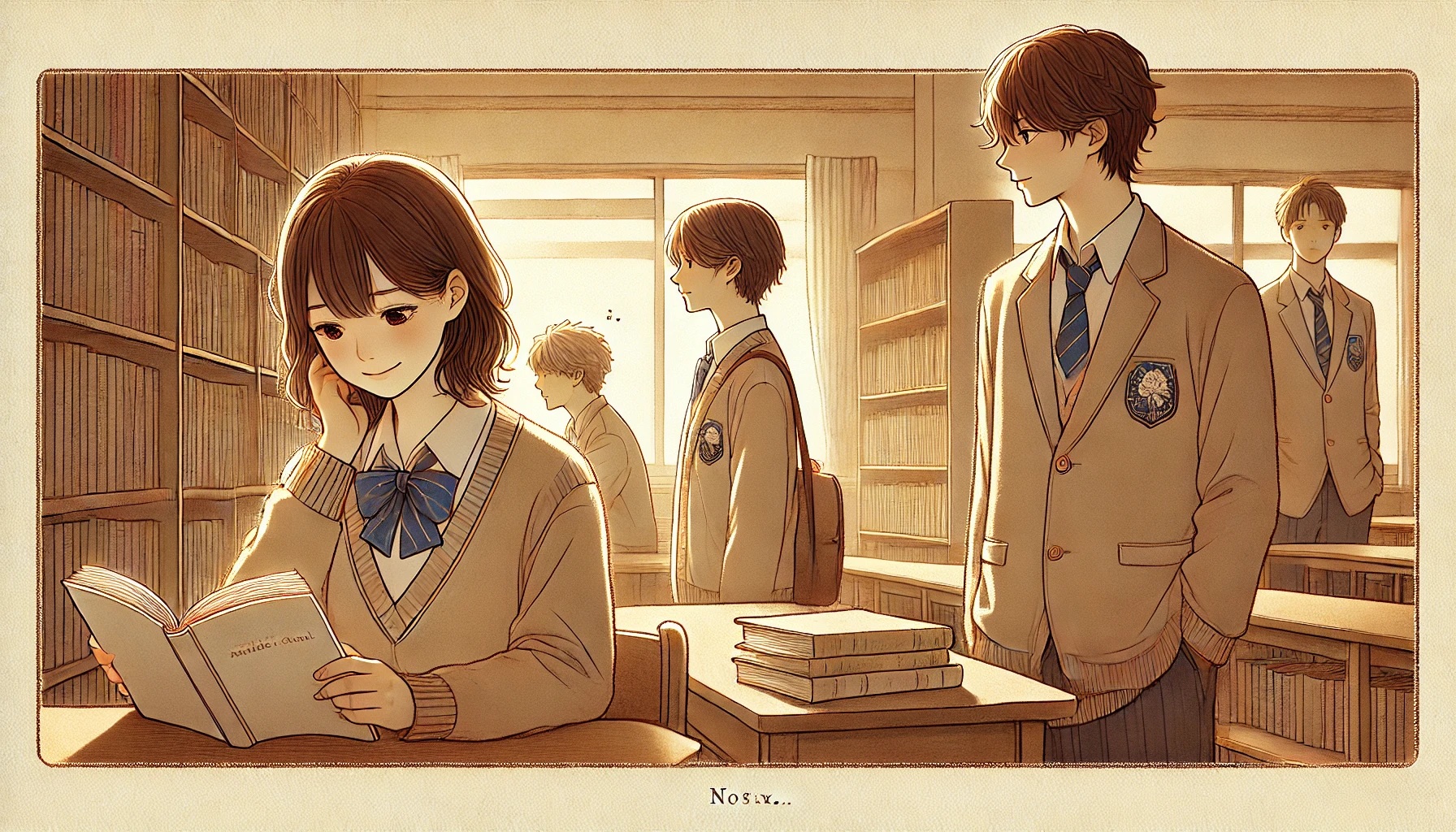
トラブルが起きたときの対処法
嫌なことを言われたらどうする?
学校生活の中で、誰かから嫌なことを言われることはあるかもしれません。
たとえ冗談のつもりでも、受け取る側がつらいと感じたら、それは立派なトラブルです。
まず大切なのは、「我慢しすぎないこと」です。
嫌なことを言われたときは、すぐに反応せず、一度深呼吸して心を落ち着けましょう。
そのうえで、「それはちょっと傷つくな」と静かに伝えられたら理想です。
でも、直接言い返すのが難しい場合は、無理をする必要はありません。
その代わり、信頼できる友達や先生、保護者などに相談してみましょう。
話すことで気持ちが軽くなることもありますし、第三者の意見から新しい視点が得られることもあります。
自分に原因があると思い込まないでください。
人を傷つけるような言葉を使う側に問題があります。
あなたには安心できる環境にいる権利があります。
小さなことでも、心が「嫌だな」と感じたら、それは無視していいことではありません。
自分の気持ちを大切にして、一人で抱え込まないことが一番大切です。
SNSでのトラブルに巻き込まれたら
今の中学生にとって、SNSやチャットアプリは日常の一部ですよね。
でも、そこには思わぬトラブルが隠れていることもあります。
たとえば、「LINEグループで無視された」「SNSに自分の悪口が書かれていた」など、ネット上でのいじめやトラブルは、心に深い傷を残します。
まず知っておいてほしいのは、SNSは“証拠”が残るということ。
嫌なメッセージや画像を見つけたら、すぐに削除せず、スクリーンショットをとっておくことが大事です。
その証拠をもとに、大人や先生に相談しやすくなります。
また、自分が不快だと感じるアカウントやグループからは、思い切って距離を取ることも大切です。
ミュート、ブロック、非表示など、自分を守るための機能を使いましょう。
SNSでのやりとりは誤解も生まれやすく、ちょっとした言葉の違いがトラブルに発展することもあります。
だからこそ、何かあったときには一人で悩まず、信頼できる大人に相談してください。
早めの行動が、心を守るカギになります。
ケンカしたときの仲直りの仕方
友達とのケンカは、決して悪いことではありません。
本音をぶつけ合ったからこそ、お互いの気持ちがわかるきっかけになることもあります。
大事なのは、「どう仲直りするか」です。
まずは時間を少し置いて、お互いの気持ちが落ち着くのを待ちましょう。
すぐに謝らなくても、心の整理をする時間が必要なこともあります。
そのうえで、「あのときはごめんね」「ちょっと言いすぎちゃった」と、自分の非を素直に認めることができると、相手の気持ちもやわらぎやすくなります。
もちろん、相手にも悪いところがあったとしても、まずは自分から歩み寄る気持ちを見せることが大切です。
言いにくいときは、手紙やメッセージで気持ちを伝えるのもおすすめです。
ケンカをしたからといって、すぐに仲直りできるとは限りません。
でも、相手を思いやる気持ちと、自分の気持ちを伝える勇気があれば、関係を修復することはできます。
ケンカの後にわかり合えた友情は、もっと強くなれることもありますよ。
先生や親に相談するタイミング
人間関係のトラブルで困ったとき、誰かに相談するのって、ちょっと勇気がいりますよね。
「こんなことで相談してもいいのかな?」と思ってしまうかもしれません。
でも、大人に相談することは、“助けを求める勇気”です。
決して弱いことではありません。
目安としては、
-
何日もモヤモヤして心がつらいとき
-
誰にも話せず一人で悩んでいるとき
-
自分や友達が傷ついていると感じたとき
こういったときには、遠慮せず大人を頼ってください。
先生、保護者、スクールカウンセラーなど、話を聞いてくれる人はたくさんいます。
自分の言葉でうまく説明できなくても大丈夫。
「うまく話せないけど、ちょっと相談したいことがある」と一言伝えるだけでいいんです。
早めに相談すれば、それだけ早く問題も解決に向かいます。
信頼できる大人と一緒に考えることで、心がぐっとラクになることもありますよ。
「無視」や「いじめ」に気づいたら
もし、自分や友達が無視されたり、いじめられていると気づいたら、まず覚えておいてほしいのは「見て見ぬふりをしない」ことです。
いじめは、心の深いところに傷を残します。
そして、時間が経つほどにエスカレートすることもあります。
まず、自分がいじめられていると感じたら、「自分が悪いからだ」と思わないでください。
いじめをする側に100%の責任があります。
あなたの尊厳や人権が傷つけられていることに、しっかり気づいてください。
そのうえで、先生や保護者、スクールカウンセラーにすぐに相談しましょう。
証拠がある場合(メッセージ、ノート、動画など)は、それを残しておくことも大事です。
また、周囲でいじめを見かけたときも、「自分には関係ない」と思わずに、信頼できる大人に伝えてください。
あなたの行動が、誰かを助けることになります。
いじめは、絶対に許されないことです。
そして、助けを求めることは、何よりも勇気ある行動です。
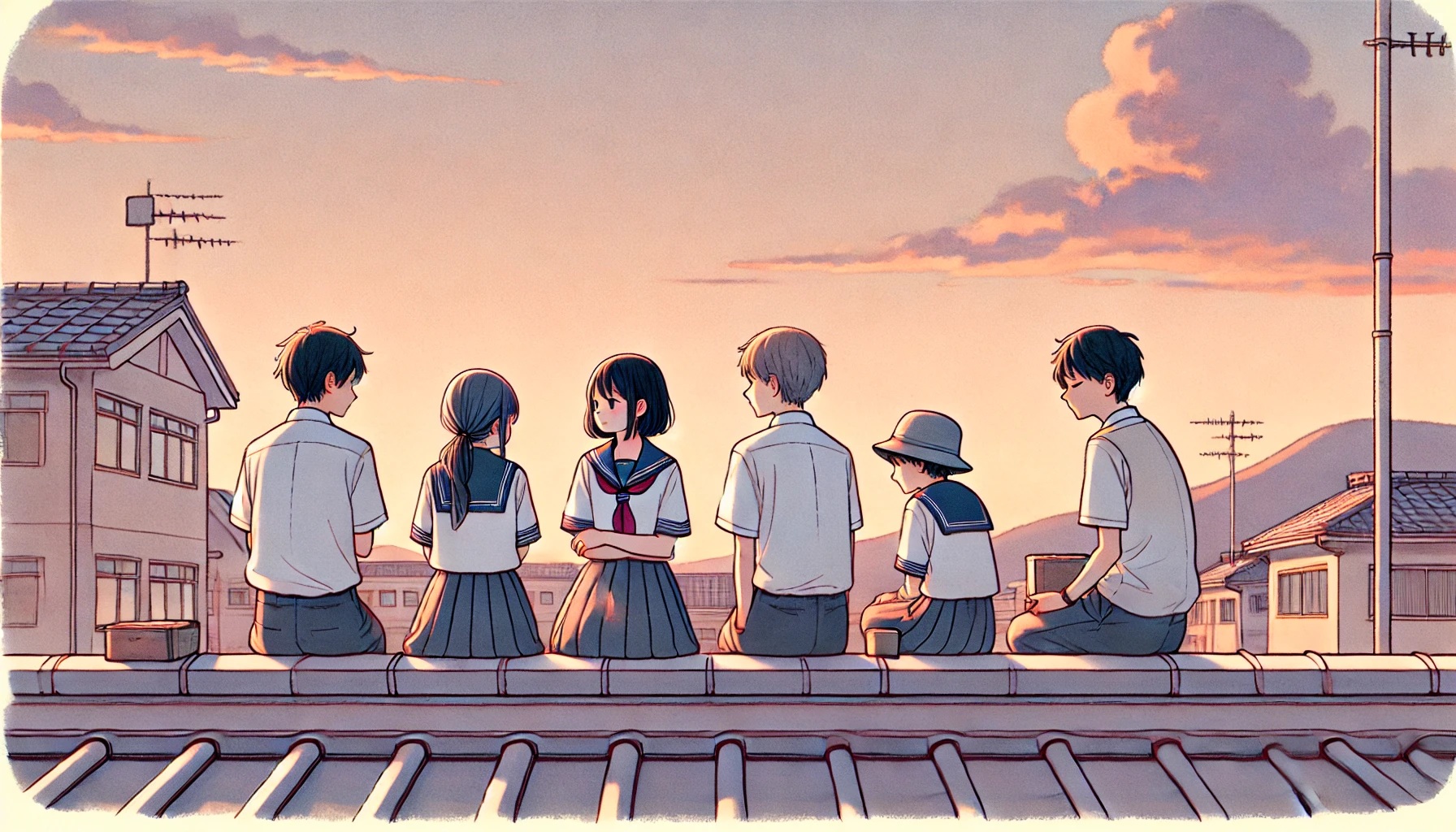
良い友達関係を育てるためにできること
「ありがとう」と「ごめんね」が言える関係
友達と良い関係を続けるために、いちばん大切なことは何でしょうか?
それは、「ありがとう」と「ごめんね」が素直に言える関係をつくることです。
「ありがとう」は、感謝の気持ちを伝える魔法の言葉です。
何か手伝ってくれたとき、一緒に笑ってくれたとき、ちょっとしたことでも「ありがとう」と伝えるだけで、相手の気持ちはとても温かくなります。
逆に、「ごめんね」と謝ることも、関係を深める大事なポイントです。
失敗したときや言いすぎたときに、自分の非を認めて謝ることができる人は信頼されます。
ただ、どちらの言葉も、無理に使うのではなく「本当にそう思ったとき」に伝えるのが大事です。
その気持ちが相手にちゃんと伝わって、「この人と一緒にいると安心する」と感じてもらえるようになります。
小さな「ありがとう」や「ごめんね」を重ねることで、友情は少しずつ深まっていきます。
毎日のやりとりの中で、気持ちを言葉にすることを忘れずにいたいですね。
相手の話をちゃんと聞く大切さ
友達関係でとても大切なのが、「話を聞くこと」です。
話すことばかりに集中してしまうと、相手の気持ちを見逃してしまうこともあります。
だからこそ、相手の話にしっかり耳をかたむけることが大事なんです。
たとえば、友達が悩みごとを話してきたとき、途中で話をさえぎって自分の話をしてしまうと、相手は「ちゃんと聞いてくれてない」と感じてしまいます。
逆に、「うん、そうなんだ」「それはつらかったね」と共感しながら聞くと、安心して本音を話してくれるようになります。
また、話を聞くときは、相手の目を見たり、うなずいたりすることもポイントです。
そうすることで、「ちゃんと聞いてるよ」という気持ちが伝わります。
友達との信頼関係は、「聞く力」から育つことがとても多いです。
相手を大切に思う気持ちがあるなら、まずはその人の話をしっかり聞くことから始めてみましょう。
それが、お互いに安心できる関係をつくる第一歩になります。
自分の気持ちを上手に伝えるコツ
仲の良い友達とでも、気持ちを伝えるのが難しいことってありますよね。
「こんなこと言ったら嫌われるかも」
「どう伝えたらいいかわからない」
そんなふうに感じたこと、きっと誰にでもあります。
でも、自分の気持ちをきちんと伝えることは、とても大事なことです。
本音を言えずにガマンし続けていると、いつか心がしんどくなってしまいます。
上手に気持ちを伝えるコツは、「○○してくれてうれしかった」「○○はちょっと困ったな」というように、自分の感じたことを主語にして話すことです。
たとえば、「○○ちゃんって、いつも話を聞いてくれてうれしいな」と言えば、相手もうれしくなります。
逆に、「昨日のこと、ちょっとびっくりしちゃった」と伝えれば、相手も気づいてくれるかもしれません。
大切なのは、相手を責めるのではなく、自分の気持ちをやさしく伝えること。
そのやりとりを通して、お互いをもっと理解し合えるようになります。
言葉にするのが難しいときは、メモに書いたり、タイミングを見て伝えるのもOKです。
自分の気持ちを大切にすることは、相手を大切にすることにもつながるんです。
助け合う経験が友情を深める
友達との絆を深めるには、「助け合うこと」がとても大切です。
困ったときに助けてもらったことがある人は、そのありがたさをよく知っていると思います。
逆に、自分が誰かを助けたことで、関係がグッと近くなった経験もあるかもしれません。
助け合いは、ちょっとしたことでいいんです。
教科書を忘れた友達に見せてあげる。
プリントを落としたのを拾ってあげる。
体育のときに手を貸してあげる。
そんな日常の中の小さな行動が、相手の心に残ることってたくさんあります。
また、助けられた側も「ありがとう」と素直に伝えることで、気持ちのキャッチボールが生まれます。
そのやりとりが、信頼関係の土台になります。
もちろん、無理して助ける必要はありません。
自分にできる範囲で、ちょっとした気づかいや行動ができれば、それで十分です。
助け合うことで、「この人と一緒にいると安心する」という気持ちが育ちます。
それが、長く続く友情へとつながっていくんです。
お互いに成長できる関係とは?
本当に良い友達関係とは、「一緒にいることで自分も相手も成長できる関係」です。
つまり、ただ楽しいだけじゃなく、お互いを支え合って高め合えるような関係のことです。
たとえば、「あの子ががんばってるから、私もがんばろう」と思える友達。
「間違ってたら注意してくれるけど、ちゃんとフォローしてくれる」そんな人がそばにいると、自分もどんどん成長できます。
お互いに違うところがあるからこそ、学べることもたくさんあります。
意見がぶつかったときに話し合える力も、信頼関係があるからこそ生まれます。
また、自分のことをしっかり見てくれる友達は、いいところも悪いところも正直に伝えてくれます。
それを受け入れて、お互いによりよくなっていこうとする姿勢が、強い絆につながります。
「この人と一緒にいると前向きな気持ちになれる」
そんな関係を目指していくことで、今だけでなくこれから先も続く友情が育っていきます。

親ができるサポートとは?
子どもの友達関係にどう関わるべき?
子どもが中学生になると、友達との関係がどんどん複雑になっていきます。
親としては「ちゃんとやっていけてるかな?」と心配になることも多いですよね。
でも、親が無理に関わろうとすると、子どもは「干渉されてる」と感じてしまうことがあります。
だからこそ、関わり方にはちょっとしたコツが必要です。
まず大事なのは、「そっと見守る姿勢」です。
困っていそうな様子があっても、まずは否定せずに「話したくなったらいつでも聞くよ」と伝えておきましょう。
また、友達関係について話してくれたときには、アドバイスよりも「聞くこと」に集中してください。
子どもは“自分の気持ちをわかってくれる人”を求めています。
どうしてもアドバイスしたいときは、「お母さん(お父さん)だったら、こうするかな」と自分の考えとして話すと、子どもも受け入れやすくなります。
親ができるのは、「安心できる家」をつくること。
その安心感があるからこそ、子どもは外でがんばれるのです。
聞き役としての親の大事な役割
中学生の子どもにとって、家での会話はとても貴重な安心の場です。
その中で、親が「聞き役」になることはとても大切なサポートになります。
話を聞くときに大切なのは、途中で口をはさまないことです。
「それはこうしなさい!」とアドバイスをしたくなっても、まずは最後までしっかり聞いてあげてください。
うなずいたり、「そうだったんだね」と気持ちに寄り添う言葉をかけることで、子どもは「話してよかった」と感じます。
また、話の内容が小さなことでも、「そんなこと気にしなくていい」と言わずに、ちゃんと受け止めましょう。
子どもにとっては、その“小さなこと”がすごく大事な悩みだったりします。
聞くことに徹するだけで、子どもの心は驚くほど軽くなります。
親が聞き役になることで、家庭が「安心して帰ってこられる場所」になるのです。
子どもが悩んでいそうなときのサイン
中学生は、自分の気持ちを言葉でうまく伝えるのが難しいことがあります。
そのため、悩んでいるときでも「大丈夫」と言ってしまうことがよくあります。
そんなときは、言葉よりも「行動の変化」に注目しましょう。
たとえば、
-
いつもより口数が少ない
-
食欲がない
-
学校の話をしたがらない
-
スマホばかり見ている
-
急に怒りっぽくなった
こうした変化が見られたら、もしかすると友達関係で悩んでいるサインかもしれません。
大事なのは、「どうしたの?」と問い詰めるのではなく、「最近ちょっと元気ないように見えるけど、気になることがあったらいつでも話してね」と優しく伝えることです。
子どもが安心して話せるようになるには、時間がかかることもあります。
でも、「いつでも話せる環境」をつくっておくことで、いざというときに子どもは頼ってきてくれます。
学校との連携でできること
もし子どもの友達関係に大きな問題があると感じたら、学校と連携することも大切です。
親だけで抱え込まず、先生やスクールカウンセラーなどのサポートを受けることで、より適切な対応ができます。
学校と話すときは、事実を冷静に伝えることがポイントです。
「いつから」「どんなことが起きているか」を具体的にまとめておくと、先生も動きやすくなります。
また、先生と連絡を取る際には、「子どもが安心して学校生活を送れるように、一緒に考えていきたい」という協力的な姿勢を持ちましょう。
子どもが「学校で見守ってくれている人がいる」と感じられるだけで、安心感は大きくなります。
問題が大きくなる前に、早めに連携することが、子どもを守る一番の方法です。
保護者も学校も、同じ「子どもの味方」であることを忘れないでください。
親自身も子どもと一緒に成長しよう
親もまた、子どもとの関わりを通じて成長していける存在です。
友達関係に悩む子どもに寄り添う中で、「どう接すればいいのか」「何を信じればいいのか」と迷うこともあるでしょう。
でも、その“迷いながらも向き合う姿勢”こそが、子どもにとって一番の安心につながります。
子どもは、親の背中をよく見ています。
だからこそ、「一緒に考えてくれる大人がいる」と感じるだけで、心が支えられるのです。
完ぺきな親である必要はありません。
「わからないけど、あなたのことを大事に思っているよ」と伝えるだけで、子どもは十分に救われます。
子どもと同じように、親も悩み、考え、学びながら前に進んでいきましょう。
その姿が、親子の信頼関係をより深くしてくれるはずです。
まとめ
中学生の友達関係は、思春期ならではの悩みや戸惑いがたくさんあります。
ちょっとしたすれ違いで距離ができたり、誰とも話せない日があったり。
SNSでのトラブルや、グループから外れたように感じる不安も、誰にでも起こりうることです。
でも大切なのは、「一人で抱え込まないこと」。
本当の友達関係とは、お互いに自然体でいられて、支え合える関係です。
無理して合わせたり、我慢ばかりする必要はありません。
そして、親も子どもを見守りながら、少し距離をとってサポートしていくことが大切です。
家庭が安心できる場所であることで、子どもは外の世界でもがんばれる力を持てるようになります。
どんな関係も一歩ずつ。
焦らず、少しずつ築いていけば、きっと心から信頼できる友達に出会えるはずです。
この記事が、そんな「大切な一歩」を踏み出すヒントになればうれしいです。



コメント